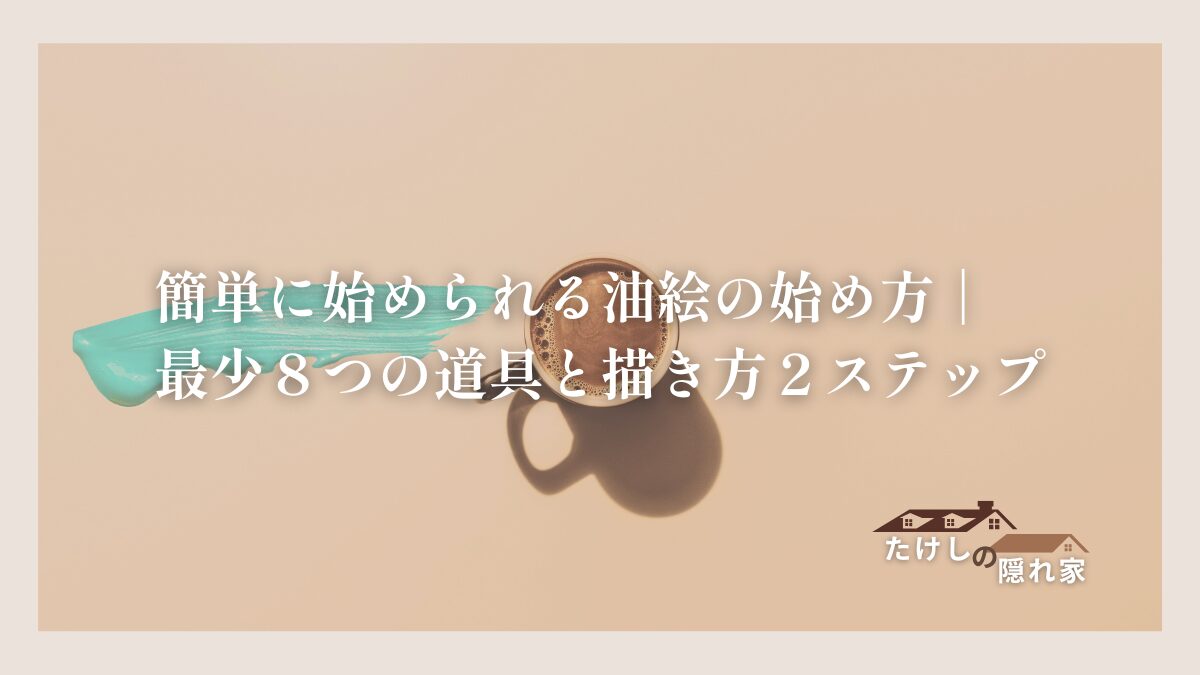「油絵を始めてみたいけど、なんだか難しそう…」
「道具が多そうで、ハードルが高い気がする」
そんな風に感じていませんか?
こんにちは、「たけしの隠れ家」のたけしです。
僕も最初はそうでした。
なにから揃えたらいいのか…
どうやって描けばいいのか…
手が止まってしまって。
でも、やってみると意外とシンプルで、「これでいいんだ」って思えたんです。
この記事では、ゆったり、気楽に始められる油絵のコツをお伝えします。
ほんのちょっとの道具と、ほんの少しの勇気があれば、もう充分なんです。
この記事では「最低限これだけでOK」な道具と、「ゆるく始める描き方」をやさしくお伝えします。
- 油絵が初心者向けな理由3つ
- 最初にそろえる道具は8つでOK
- たったこれだけ!油絵の描き方2ステップ
もし続きが気になる場合は、記事を読み進めてみてください。
★もくじ★
「油絵って難しそう…」そんなあなたへ

油絵ははじめる前から「ムリムリ!」と思ってしまうかもしれません。
なぜなら、学生時代にほとんど使うことがなかったから。
私は中学生の時に油絵を描いたことがありましたが、たった一回でした(笑)
水彩絵の具は持たされるのに、油絵は全くといいほど触れる機会がないですよね。
だから、そもそも絵を描くときの候補にすらあがってこないと思います。
そんな理由から、油絵は難しいイメージが定着しているんだと思います。
道具の買い方もわからなければ、もちろん描き方なんて未知の世界ですよね。
油絵を難しく考えすぎないで大丈夫な理由

油絵は難しく考えすぎなくて大丈夫です。
それは、なぜかと言うと以下のようなメリットがあるからです。
- 重ねて塗ることができる
- 修正が簡単
- 乾きが遅い
順番に解説していきます。
重ねて塗ることができる
油絵は重ねて塗ることができます。
油絵は乾いてしまえば、乾いた上から塗り重ねても溶け出さないからです。
一方、水彩画だったら色を塗り重ねることは難しくなってしまいます。
なぜなら、前回塗った下の色が溶け出してしまうからです。
結果的に、水彩画の場合は下の色が溶け出して色が濁ってしまいます。
そうなると、せっかく塗った作品が台無しです。
一方油絵は、一度固まるとガチガチに固まって再び溶け出すことがないので、重ね塗りが簡単です!
乾きが遅い
油絵の具は乾きが遅いです。
油絵が乾く仕組み
これは、「酸化重合」といって酸素を取り込んで徐々に固まっていくからです。
具体的には、
- 表面乾燥→1週間くらい~
- 完全乾燥→半年くらい~
「表面乾燥」は、指で触っても油絵の具が手にくっつかない状況(指触乾燥)をいいます。
「完全乾燥」は、油絵の中の方まで乾燥した状態のことをいいます。
油絵は、表面から中の方に向かって徐々に乾燥していくんですね。
水溶性の絵の具が乾く仕組み
一方、水で溶ける性質(水溶性)の「水彩絵の具」や「アクリル絵の具」が乾く仕組みは「水分の蒸発」です。
- 水分が蒸発→糊によって顔料が紙に定着
という流れで乾きます。
いかに油絵の具の乾きが遅いかがわかるかと思います。
「乾きが遅いと何がいいか」といいますと、「全体的に焦ることがない」というメリットがあります。
- じっくり色づくりできる
- さっき作った色をもう一度使える
- ゆっくりぼかすことができる
などなど、焦らずにゆったりと作品づくりができますよ。
修正が簡単
油絵はまちがった色を塗った場合、簡単に修正ができます。
まちがったら「布で拭い取る」か「乾いたあと絵の具で消す」ことができるからです。
さきほどのご説明のとおり、油絵の具は乾くまで時間がかかります。
ですので、布で拭い取ることができます。
また、もし乾いたとしても絵の具で消してからもう一度絵を描くことができます。
でも水彩画だったら、こうはいきません。
水彩画の場合は、拭い取ったら紙が破けますし、前回描いた色が再び溶け出したりして修正できません。
油絵初心者が抱える問題は色づくりがうまくいかなかったり、思ったように描けなかったりすることだと思います。
なので、簡単に修正ができるのはとても大きなメリットになるはずです。
だから、
「あっ、まちがえた!」と思った時も大丈夫。
サッとふき取るだけで、リセットできますよ。
これは、忙しい日々のなかでちょこっと描きたい人にとって、ほんとうに心強い味方です。
上記の3つの理由から、油絵の具は初心者向きと言えると思います。
油絵をゆる〜く始めるための最小限8つの道具

ここからは、油絵をゆる〜く始めるための道具と描き方をご紹介していきます。
まずは必要な道具から見ていきましょう!
- 支持体
- 油絵具
- 筆
- パレット
- 油(ペインティングオイル)
- 絵皿
- 筆洗油
- 油壺
以上です。
簡単に説明していきますね。
支持体
まずは支持体です。
支持体とは、「キャンバス」や「紙」のように「絵の具を支える材料」のことを言います。
支持体選びは結構重要かなと思います。
筆運びや出したい表現に影響するからです。
例えば、
- 細かい絵を描きたい→凹凸がない支持体
- かすれた感じを出したい→凹凸のある支持体
上記のような感じで、あなたが
「どんな絵を描きたいか」
によって支持体の選び方が変わっていくと思います。
どんな支持体があるか
油絵は、主に「キャンバス」「木製パネル」に描くことになると思います。あとは、「キャンバスボード」や「油彩紙」というものがあります。
特徴は以下のとおりです。
- キャンバス→キャンバス生地で凹凸がある
- 木製パネル→表面の凹凸がなくスベスベ
- キャンバスボード→キャンバス生地のように凹凸がある
- 油彩紙→キャンバス生地のように凹凸があるが滑らか
初心者の方は、油彩紙がおすすめです。
理由は、以下です。
- かさばらない
- 自由にカットできる
- 下地を塗らなくてもすぐに油絵が描ける
こんな感じで初心者にもメリットが多いです。
私は油彩紙をカットして作品を描き、額装したものを個展で展示しました。
油絵具(最低限の色)
続いて油絵の具です。
油絵の具を選ぶ基準は以下のとおりです。
- 色数
- ブランド
- 透明度
以上です。
色数
まず「色数」です。
色数は特に重要です。
なぜかと言うと、初心者は色づくり(混色)がなかなかうまくいかないからです。
「混色」とは、目的の色にするために2色以上の色を混ぜ合わせることを言います。
例えば、空の色を塗るのには「白」と「青」を混ぜるのですが、鮮やかな色が出せなかったりします。
「白」にも「青」にも様々な特徴を持った色があります。
ですので、同じ色でも複数持っていないといけなかったりするわけです。
なので、セットで買っても足りない可能性があります。
ちなみに私は油絵の具のチューブを13色くらい使っています。
ブランド
次に「ブランド」です。
ブランドは、主に日本のものと海外のものがあります。
メーカーによって、名前が違ったり配合が違ったりするので、これはお好みでいいです。
あなたが好きなメーカーの油絵の具を探せばよいかと思います。
私は、特に違いがわかりません(笑)
日本と海外の油絵の具の主な違いは、チューブのカタカナ表記のあるなしです。
英語だとぱっと見てすぐには頭に入ってこない場合がありますが、日本のメーカーだとカタカナ表記の場合が多いので、すぐに何の色かがわかります。
とはいえ、油絵の具チューブの色と、油絵の具の色は同じ場合が多いので英語でも問題ないと思います。
ちなみに私は「Winsor & Newton」というイギリスのブランドの油絵の具を使っています。
Winsor & Newtonを使い始めた理由は、私の好きな画家が使っていたからです。
僕の持っている油絵の具
- 「白」チタニウムホワイト
- 「黄」カドミウムイエロー
- 「赤」カドミウムレッド
- 「黄土」イエローオーカー
- 「緑」カドミウムグリーン ※ホルベイン
- 「茶」バーントシェンナ
- 「紫」マゼンタ
- 「青」プルシャンブルー
- 「青」フレンチウルトラマリン
- 「灰」ペインズグレー
- 「緑」サップグリーン
日本のメーカーですと「クサカベ」「ホルベイン」「マツダ」が有名です。
透明度
最後に「透明度」です。
油絵の具には主に3つの透明度があります。
- 透明
- 不透明
- 半透明
油絵の具には色によって透明度が記載されています。
簡単に説明すると、「透明色」は下の絵の具の色を透かすことができます。透明色のさまざまな色を重ねることで色が複雑になり、深みのある表現になります。
反対に「不透明色」は覆い隠す力が強い色で、色がとても目立ちます。
そして、最後の「半透明色」ですが、お気づきの方もいると思いますが、透明色と不透明色の中間の要素を持ちます。
ですので、下の色を半分透かしてくれる色だと思ってもらえれば良いですね。
ここで透明度の使い分けの考え方なんですが、
- 不透明色は明るい部分に塗る
- 透明色は暗い部分に塗る
と覚えておけば良いです。
そうすることによって、立体感が生まれます。
ちなみに私が持っている油絵の具で透明度を表記すると、以下のようになります。
- 「白」チタニウムホワイト→不透明色
- 「黄」カドミウムイエロー→不透明色
- 「赤」カドミウムレッド→不透明色
- 「黄土」イエローオーカー→半透明色
- 「緑」カドミウムグリーン→不透明色 ※ホルベイン
- 「茶」バーントシェンナ→透明色
- 「紫」マゼンタ→透明色
- 「青」プルシャンブルー→透明色
- 「青」フレンチウルトラマリン→透明色
- 「灰」ペインズグレー→半透明
- 「緑」サップグリーン→透明色
筆
つづいて筆についてです。
筆を選ぶポイントは、
- 形
- 太さ
- 毛の種類
以上です。
一つずつ説明していきますね。
形
まずは、筆の「形」です。
筆の形はさまざまありすぎて、初心者の方には選ぶのが難しいと思います。
ですが、形の選び方としての基準は「好きな描き方」で選べばいいと思います。
例えば、
- 大きな面積を一筆で一気に塗るのが好きなら「平筆」
- 細かい描写が好きなら「丸筆」
というようにすれば良いですね。
ちなみに私は、平筆が好きです。
理由は、なるべく少ない手数で色を出したいからです。
また、ナイロンの平筆は油絵の具の粘度に負けないので、あまりオイルをつけなくても塗ることができます。
私は丸筆では色が弱々しくなってしまうのですが、平筆ではその弱点をカバーしてくれます。
そういう理由から平筆をメインに使っています。
太さ
次に筆の太さです。
筆の太さは2~3種類くらい持っていれば良いと思います。
筆には「号数」というものがあります。
数字が大きくなると、筆が太くなっていきます。
支持体のサイズが大きくなれば2~3種類では少ないかもしれませんが、200×200㎜くらいのサイズでしたら2~3種類くらいあれば絵が描けます。
ちなみに私は、0・2・6号の筆で200×200㎜の絵を描いています。
同じ号数でも、メーカーによってサイズが違う場合があるので、幅を確認しておきましょう。
毛の種類
次に毛の種類です。
毛の種類は本当にたくさんあります。
まず大きく天然毛と人工毛があります。
天然毛は、動物の毛が使われています。
一方、人工毛はナイロン素材のものが中心です。
筆の硬さは天然毛も人工毛もさまざまあります。
選び方ですが、あなたが「どんな絵を描きたいか」で決めていきましょう。
- 細かくて繊細な絵を描きたいのであれば→細くて柔らかめのナイロンの丸筆
- 筆跡を残して迫力あるタッチを出したいのであれば→硬くて大きめの豚毛の平筆
という具合です。
パレット
パレットについて説明していきます。
パレットを選ぶ基準は3つで、
- 素材
- 大きさ
- 形状
です。
素材
まず、素材です。
油絵パレットの素材は、主に
- 木製
- 紙
があります。
それぞれに一長一短がありますが、何が大きく違うかと言いますと、制作後に掃除するか否かです。
木製パレットの場合、同じパレットで何度も油絵を描いていくため、毎回掃除が必要になります。
油絵の具は乾きが遅いのですが、一度乾燥するとガチガチに固まってしまいます。
そうなると取り除くのが難しくなります。
取れなくはないのですが、もともとパレットに塗られていた塗料が剥がれてしまう可能性があります。
ですので、毎回掃除するのが嫌な場合、木製パレットはおすすめしません。
一方、紙パレットは油絵の具が染み込まないように、紙にコーティングされたパレットです。
何枚も重なっているので、使ったら丸めてゴミに出すことができます。
ですので、毎回掃除する必要はありません。
その代わりずっと買い続ける必要があります。
大きさ
次に「大きさ」です。
パレットの大きさはいろいろあります。
油絵の具を絞り出す色数が多ければ、色数に対して大きさを選ぶ必要があります。
できれば描く前に、持っている油絵の具すべてを絞り出すことをおすすめします。
例えば、
持っている油絵の具すべてが12色の場合…
- パレットに絞り出す油絵の具の数=12色
という感じですね。
すべて絞り出す理由は、油絵を描いている途中で油絵の具を絞り出す手間がなくなるからです。
また、あなたの作業スペースによってもパレットの大きさが変わります。
小さなテーブルにパレットを置いて絵を描く場合、パレットが大きいと絵を描くのが大変になってしまいます。
逆に、色数が多いのにパレットが小さいと、必要な色数を絞り出せません。
上記のようにならないように、ちょうどよいサイズのパレットを選びましょう!
形状
次に「形状」です。
パレットの形状は、主に
- 楕円形
- 長方形
のものがあります。
その他の形状のものもありますが、わかりやすく2つにしています。
あと、形状の主な特徴として
- 穴あり
- 穴なし
があります。
穴がある場合は、パレットを持って描く場合に使います。
穴がない場合は、パレットを置いて描く場合に使います。
それぞれお好みですが、座って描きたいか、立って描きたいかあなたのスタイルに合わせて決めてみてくださいね。
オイル(ペインティングオイル)
次に、オイルの説明に入っていきます。
初心者の方には一番難しい部分だと思います。
画材屋さんにはたくさんのオイルが売っていてわかりませんよね。
でも、大丈夫です。
油絵を描くためのオイルは1本あればOKです。
ペインティングオイルというオイルを使えば、油絵を描き始めてから完成までこれ1本で描けます。
なので、まずはペインティングオイルを1本用意しましょう。
ちなみにオイルにはニオイがきついものがあります。
なかには具合が悪くなる場合もあります。
家族にも嫌な顔をされるかもしれないので、なるべく臭いが少ないペインティングオイルを選びましょう。
絵皿
絵皿は、ペインティングオイルを注ぐときに使います。
ですので、使わなくなった汚れていない小皿みたいなものでもOKです。
陶器なら何でも良いと思います。
200×200㎜くらいの小さい作品だったら、一回で使うオイルの量は500円玉くらいの大きさで良いです。
ちなみに私が使っている絵皿は直径10㎝ほどで、画材屋さんで購入しました。
筆洗油
筆洗油は、油絵を描いている途中、色を変えるときに洗浄するオイルのことです。
筆洗油を使って筆を洗浄するときの流れは、
- 余分な油絵の具を拭い取る
- 筆洗油につけて洗浄する
- 筆についた筆洗油を拭い取る
- ペインティングオイルをつける
- 油絵の具をつける
- 再び描画
こんな感じです。
ですが、油絵を描いているとき、いくらきれいに拭き上げても筆には微量の筆洗油がついた状態となってしまいます。
油絵の具に筆洗油をつけるのはあまり良しとされていないのです。
そこで筆洗油でおすすめするのが、揮発性油です。
揮発性油は、油絵の描き始めで使うオイルです。
揮発性油は油絵の具を溶かす力が強いので、私は筆洗油には揮発性油を使っています。
ただし、筆洗油より値段が高いです。
揮発性油も臭いがきついものがあります。
ですので、臭いがしないものがおすすめです。
油壺
最後に油壺です。
油壺はさきほどの筆洗油を入れる専用の容器です。
油壺は必ず用意したほうがいいです。
筆洗油は、揮発するからです。
揮発とは、常温で液体が気体になってしまうことを言います。つまり、空気に触れるとなくなってしまいます。
そこで、油壺があるとしっかりと密閉してくれるので、揮発することがありません。
また、油絵の具の汚れが下に溜まってくれるので、上の方はいつも澄んだ状態です。
というわけで、とても油絵を描くうえでは必要な道具です。
以上、ちょっと長くなってしまいましたが、油絵をこれからはじめようかなという人のために説明してきました。
必要最小限に絞ってご紹介したので、手軽に始められるかなと思います。
もし良かったら、一緒に油絵を描いていきましょう!
油絵のゆる〜い描き方2ステップ

道具がそろったらさっそく油絵を描いていきましょう。
ここでは、いきなり油絵の具を塗れる「油彩紙」を例に説明していきますね。
下書き(不要でもOK)
まずは下書きです。
下書きは何通りかやり方があります。
- 転写
- 大まかな形を描く
- マス目を描いてから下書き
- はかり棒で図りながら
転写
転写は、描きたい画像を印刷して、印刷した紙と支持体の間にカーボン紙をはさみ、ボールペンなどで転写する方法です。
形をなぞっていけばいいので、初心者には一番やりやすい方法かと思います。
筆でざっくり
次に筆でざっくりと描いていく方法です。
大体の構図を考え、「この辺に山があるな」とか「この辺は体だな」と大まかに一色の色で四角や丸を描いていきます。その後に徐々に形を決めていって、徐々に細部を描いていきます。
マス目を描いてから下書き
マス目を描いてから下書きする方法です。
描きたい画像を印刷して、印刷した紙に支持体と同じ比率のマス目を書きます。
このマス目の中に下書きしていきます。
マス目を作ることによって支持体が細分化され、どこに何を描けばいいのかがわかりやすくなります。
はかり棒で図りながら
はかり棒で図りながら一つ一つ大きさを見ていきます。腕を伸ばして描きたいものを図ってから支持体に同じ幅の線を引き、その繰り返しで形にしていきます。
結構時間がかかるので、初心者にはハードルが高めです。
ちなみに私は、あまりしっかりと下書きしなかったり、転写したりまちまちです。
あなたの好きなやり方で描いてみてくださいね。
下書きは必ずしないといけないわけではないので、直接描きたい場合はいきなりそのものの色を使って描いても大丈夫です。
描画(ざっくり色を置いてから重ね塗り)
続いて描画です。
つまり、絵を描いていく作業です。
下書きが終わったら、油絵を描いていきましょう!
例えば、りんごを描くとしたらりんごとりんごが置いている机があり、りんごが「モチーフ」となり、机が「背景」となります。モチーフとは、絵のメインになる物を言います。
りんごを先に描くか、机を先に描くかですが、特に決まりはありません。
好きな方から描いていきましょう。
ちなみに赤いりんごを描く場合、
りんごの赤→「そのまま」か明るすぎる場合は「青」を少量
りんごの影部分→「赤」+「緑」や「青」を少量混ぜて表現
りんごの明るい部分→「赤」+「白」+「黄」
という具合に混色して塗ります。
色もそれぞれに特徴があるので、必ずしも上記の通りにやったからといって目的の色にはならないかもしれませんが、完璧に合わせなくてもOKです。
色を混ぜて塗っていくことの楽しさを感じてみてくださいね。
乾燥時間に合わせてのんびり描こう
お伝えした通り、油絵の具が乾くまでの時間が長いです。
なので、のんびりじっくり取り組めます。
日をまたいで制作したい場合は、1週間くらい乾燥させてから再び1週間後にまた描いていきましょう!
「今日はここがうまく描けたな」「今度はこうしよう!」と、少しずつできあがっていく過程を楽しみながら描いていけたらいいですね!
油絵の始め方に関する「よくある質問(Q&A)」

ここで初心者が疑問に思う疑問をまとめました。
よくある質問
Q:パレットのどこに油絵の具を絞るの?
油絵の具は、パレットの端に並べていきます。大きさは大体十円玉くらいですね。
違う色がくっつかないように間隔をあけて絞り出しましょう。
油絵の具チューブを絞り出すときは口から遠いところから絞り出してくださいね。
Q:パレットに油絵の具を絞る順番はある?
パレットに油絵の具を絞り出す順番は決まっていません。
ただ、さまざまな並べ方があります。
- 油絵の具セットの色の順
- 色相環順
- 透明度順
ですが、結論としてはあなたが塗りやすい配置で大丈夫です。
ちなみに私は、明るい色と暗い色という風に並べています。
Q:乾くのに時間がかかる?
油絵は乾くのに、他の絵の具より時間がかかります。
指触乾燥→7~10日ほど
完全乾燥→半年~1年ほど
です。
Q:失敗したらどうするの?
油絵が失敗したら、乾かないうちは布で拭い取ることができます。
一方、乾いたあとは白色の不透明色を塗って乾燥させてから再び修正します。
Q:道具の片付けって面倒じゃない?
道具の片づけは大体5分くらいで終わってしまいます。
- 筆:筆洗油で洗浄→拭き上げ→石鹸などで洗浄
- パレット:紙パレットなら丸めてゴミ袋へ
こんな感じで片づけはそんなに時間はかからないです。
ただし、製作中は油絵の具が衣類につかないように気をつけてくださいね。
まとめ|油絵をゆるく始めて楽しもう!
- 油絵が初心者向けな理由3つ
- 最初にそろえる道具は8つでOK
- たったこれだけ!油絵の描き方2ステップ
油絵はやり方も道具も意外とシンプルです。
油絵って、構えすぎずに始めれば、日常に癒しと達成感をくれる趣味です。
ぜひ今回ご紹介した方法で、油絵を始めてみてくださいね。
一緒に油絵を描いていきましょう!